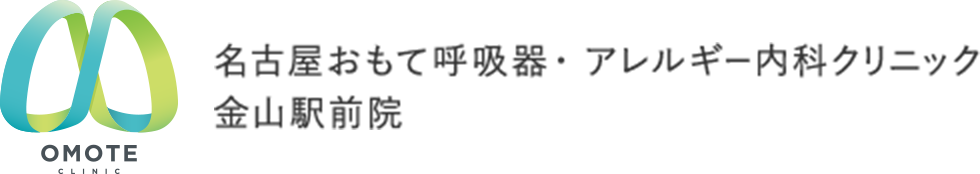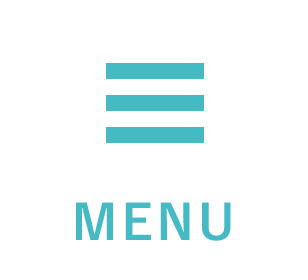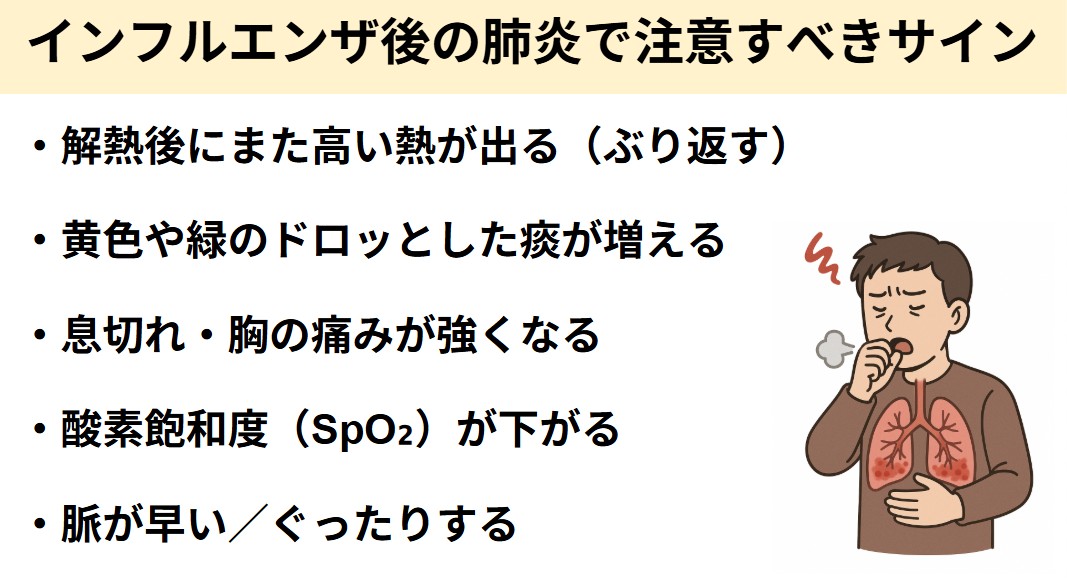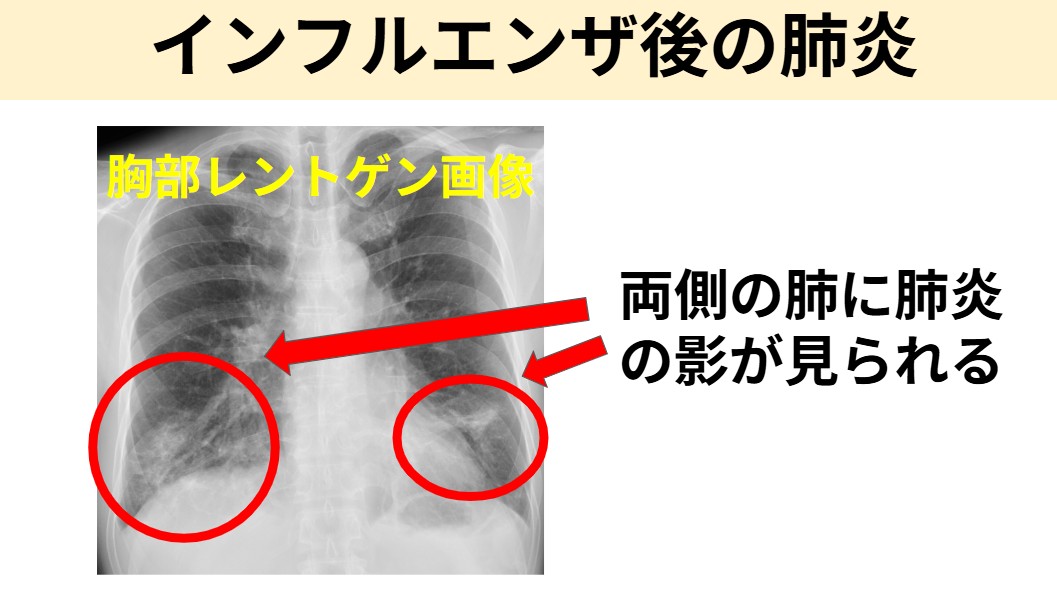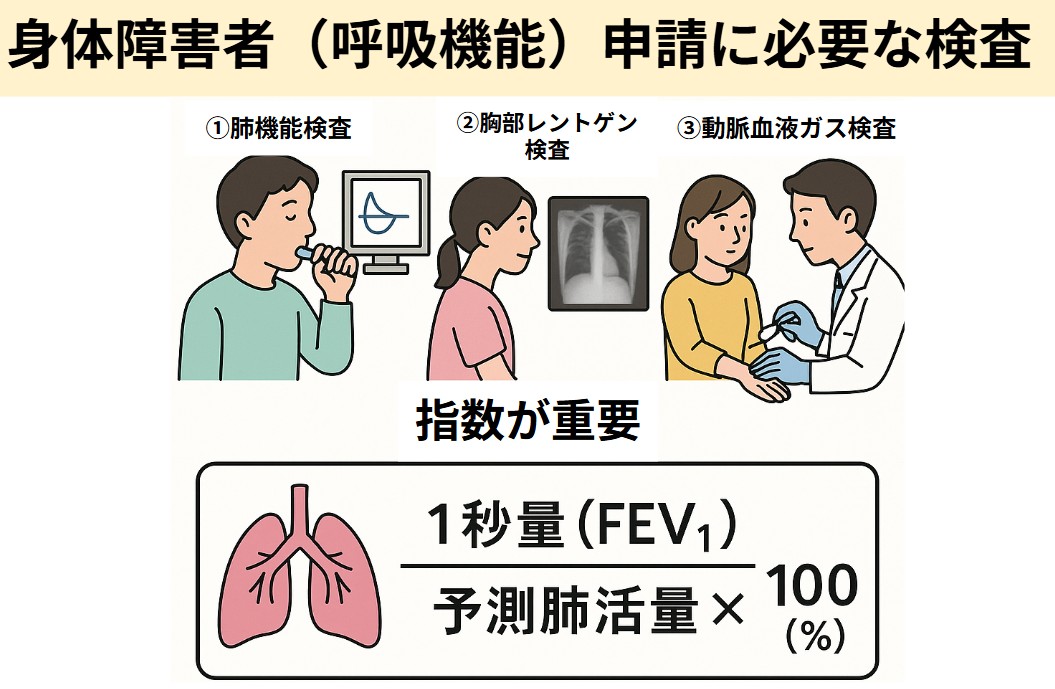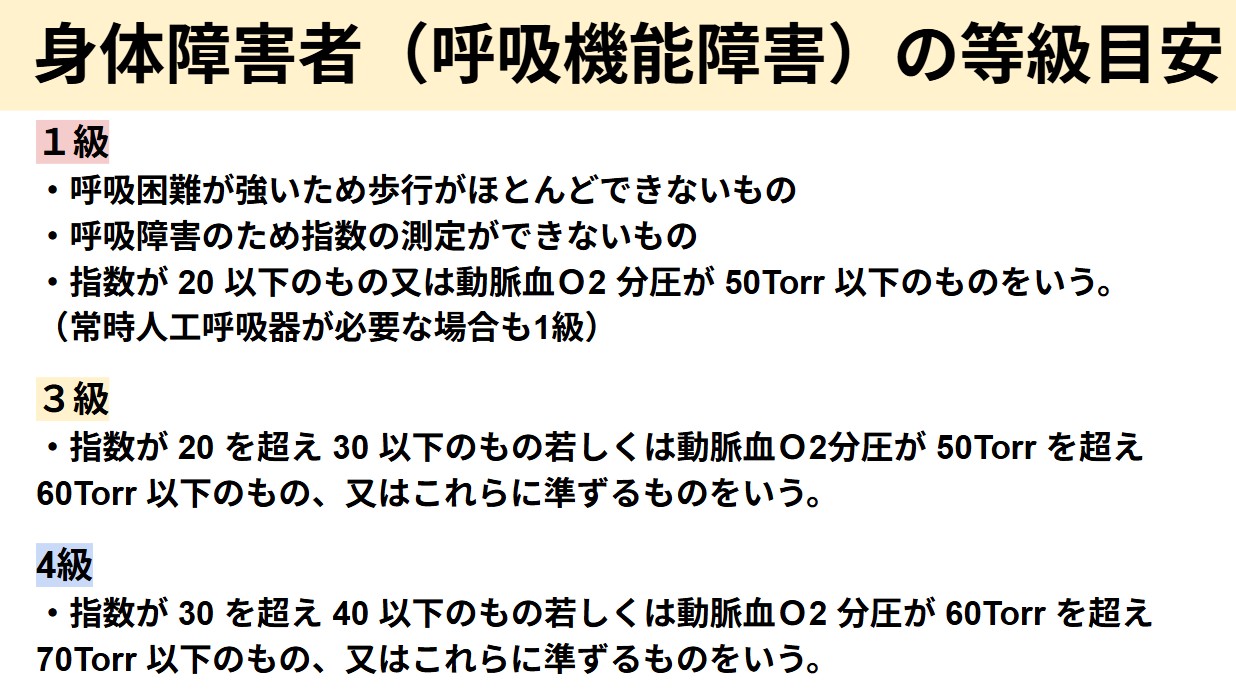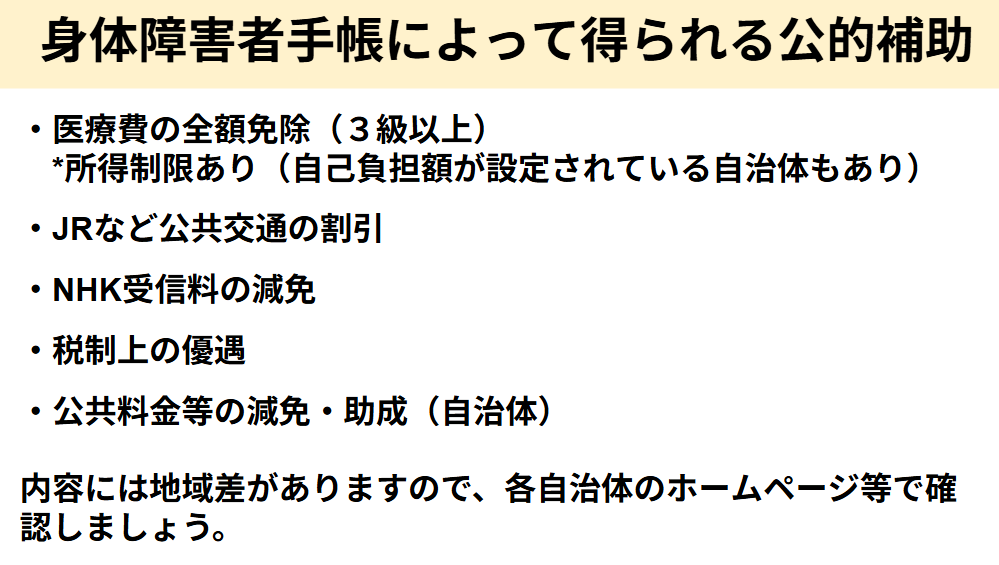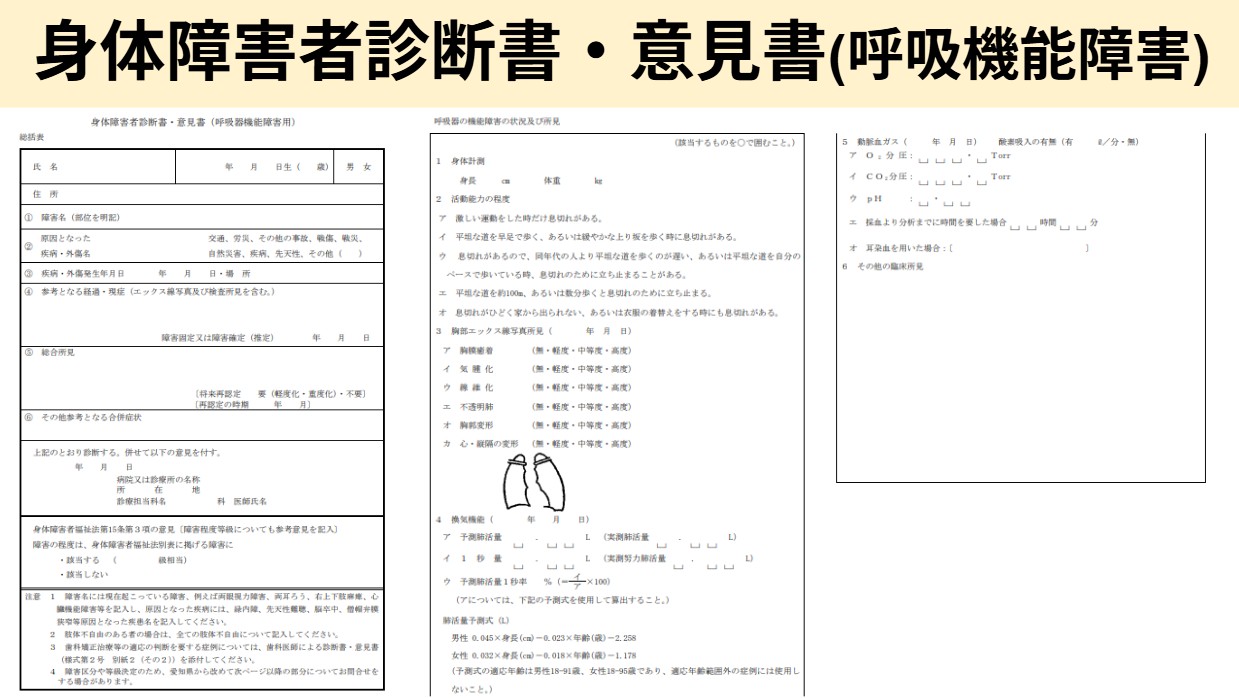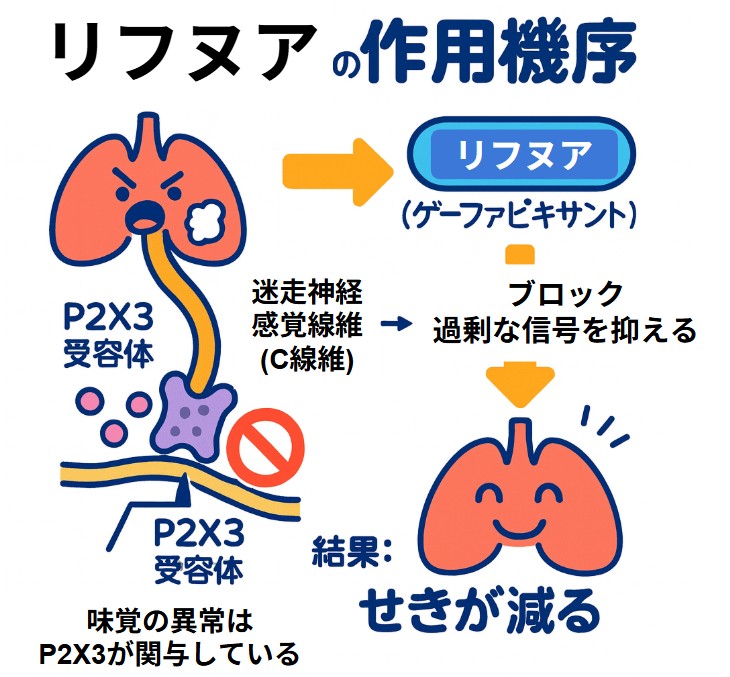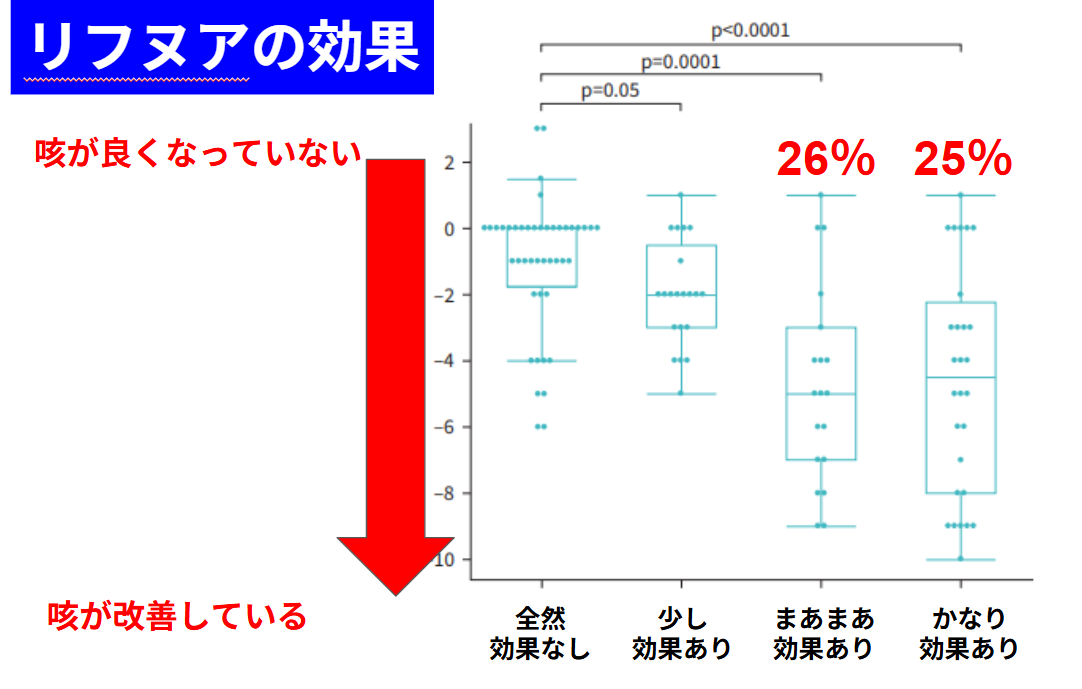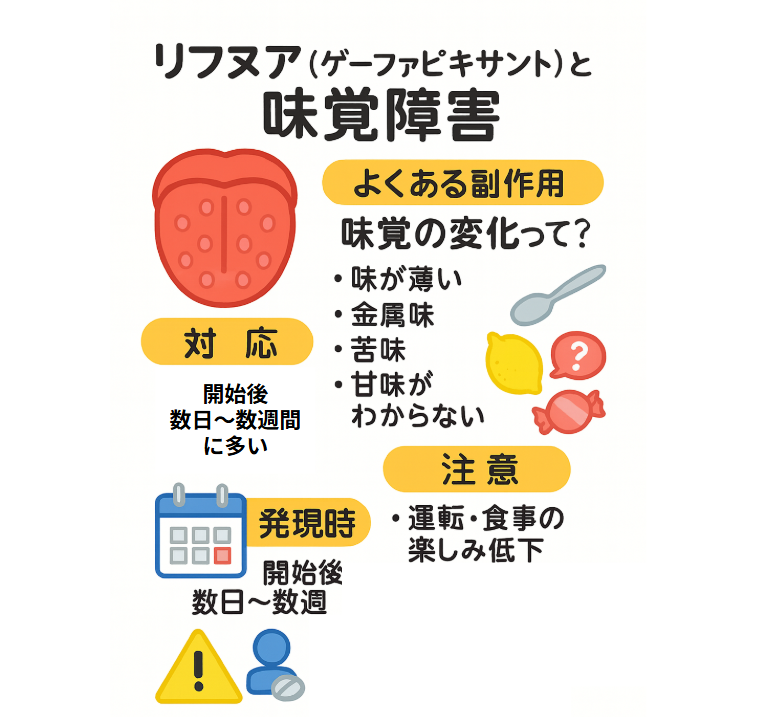睡眠中に「心臓がバクバク」——それって睡眠時無呼吸症候群?
就寝中に起きると心臓が「ドキドキ」「バクバク」しているといった症状は、睡眠時無呼吸症候群でよくみられる現象です。睡眠時無呼吸症候群は夜間の低酸素・息こらえ・交感神経の緊張を繰り返し、不整脈リスク(心房細動や期外収縮、夜間発作性頻拍など)を高めます。正しい診断と治療(CPAPなど)で動悸の改善や再発予防が期待できます。
<目次>
- 1. 睡眠中の動悸と睡眠時無呼吸の関係
2. なぜ心臓がバクバクするのか(科学的メカニズム)
3. こんな症状があれば要注意(危険サイン)
4. 自己チェック(ESS質問票)
5. 受けるべき検査(簡易検査とPSG)
6. 治療すると良くなる?(CPAPと心臓)
7. よくある質問(FAQ)
8. 当院からのメッセージ
- 1. 睡眠中の動悸と睡眠時無呼吸の関係
睡眠時無呼吸では、上気道が閉塞して呼吸が止まる→血中酸素が下がる→脳が「覚醒反応」を起こして呼吸を再開…という窒息と覚醒のミニイベントが一晩に何十回も起こります。このたび重なる交感神経*の急上昇が、夜間の動悸・頻脈・不整脈を誘発します。過去の研究でも、睡眠時無呼吸患者では心電図異常や不整脈の合併が多いことが示されています。
*交感神経は、体を「活動モード」にする神経です。緊張や運動、ストレス時に働き、心拍を速くし血圧を上げ、すぐ動ける状態を作ります。

- 2. なぜ心臓がバクバクするのか
低酸素・再酸素化の反復が活性酸素と炎症を惹起します。また陰圧負荷(息を吸おうと胸腔内圧が強く下がる)で心臓の壁応力が増大し、交感神経のサージ(カテコラミン増加)で心拍・血圧が急上昇します。長期的には心房細動や心室性不整脈の土台になります。
- 3. こんな症状があれば要注意
・家族に大きないびきや無呼吸を指摘される
・夜間の動悸・胸部不快感・息切れで目が覚める
・朝の頭痛・強い日中の眠気・集中力低下
・高血圧(特に治療抵抗性)、肥満、糖尿病、甲状腺機能異常の既往
・既往に心房細動や心不全がある
これらが重なるほど、睡眠時無呼吸と不整脈の合併リスクは高まります。
- 4. 自己チェック
下記のESS問診表が参考になります。まずは睡眠時無呼吸のセルフチェックしてみてはいかがでしょうか?
合計点が11点以上: 睡眠時無呼吸症候群の疑いが強い
合計点が5~10点: 睡眠時無呼吸症候群の疑いがある
と判断します。

- 5. 受けるべき検査
在宅簡易検査(酸素、呼吸、いびき、体位などを測る)をまず行います。自宅で2晩機械を装着して寝ることで、検査します。当院では検査機器の貸し出しを行っております。
場合によっては、さらなる精密検査である終夜睡眠ポリグラフ(PSG)を行います。こちらでは脳波などを含めて睡眠の深さも計測することができます。
- 6. 治療すると良くなる?
睡眠時無呼吸の代表的な治療であるCPAP(持続陽圧呼吸療法)は、上気道の閉塞を押し広げ、無呼吸を改善します。夜間の低酸素と交感神経サージを抑え、動悸・不整脈の誘発因子を低減します。研究では、睡眠時無呼吸症候群の患者さんで心房細動の新規発症や再発が減ることを示されています。
- 7. よくある質問(FAQ)
Q1. いびきがなくても睡眠時無呼吸で動悸は起きますか?
- 可能です。いびきは典型ですが、体位や睡眠段階によって目立たないこともあります。動悸・夜間覚醒・日中の眠気があれば検査を。
Q2. 簡易検査とPSG、どちらを受けるべき?
- スクリーニングとしては在宅簡易検査で十分なことが多く、結果や合併症でPSGを追加します。
Q3. CPAPは不整脈の再発も抑えますか?
- 研究では心房細動の発症・再発リスクの低下が示されており、特にアブレーション後の再発抑制の報告が増えています。
Q4. 自分でできる対策は?
- 減量、飲酒制限、仰向け回避、鼻閉治療。これらは無呼吸の改善に寄与し、夜間の動悸リスクを下げます。
- 8. 当院からのメッセージ
「いびき」「日中の眠気」だけでなく、夜間の動悸・息苦しさ・不整脈の背景に、睡眠時無呼吸症候群が隠れていることがあります。
睡眠中に呼吸が止まると、体は低酸素状態となり、脳が覚醒反応を起こして交感神経が急激に高まります。この負荷が一晩に何十回も繰り返されることで、高血圧・心疾患・不整脈・脳卒中のリスクが高まることが分かっています。
睡眠時無呼吸症候群は、正確な検査と適切な治療で改善が期待できる病気です。夜間の動悸が気になる方は、どうぞお気軽にご相談ください。
睡眠時無呼吸症候群の詳しい検査方法はこちら
CPAP治療に関する詳しい情報はこちら
記事作成

名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック
呼吸器内科専門医・医学博士 表紀仁
参考情報:
日本睡眠学会 睡眠障害を診断するための検査
日本呼吸器学会 睡眠時無呼吸症候群
-
Mehra R, Benjamin EJ, Shahar E, Gottlieb DJ, Nawabit R, Kirchner HL, Sahadevan J, Redline S; Sleep Heart Health Study. Association of nocturnal arrhythmias with sleep-disordered breathing: The Sleep Heart Health Study. Am J Respir Crit Care Med. 2006;173(8):910–916. doi:10.1164/rccm.200509-1442OC. PMID: 16424443.
-
Kanagala R, Murali NS, Friedman PA, Ammash NM, Gersh BJ, Ballman KV, Shamsuzzaman ASM, Somers VK. Obstructive sleep apnea and the recurrence of atrial fibrillation. Circulation. 2003;107(20):2589–2594. doi:10.1161/01.CIR.0000068337.25994.21. PMID: 12743002.